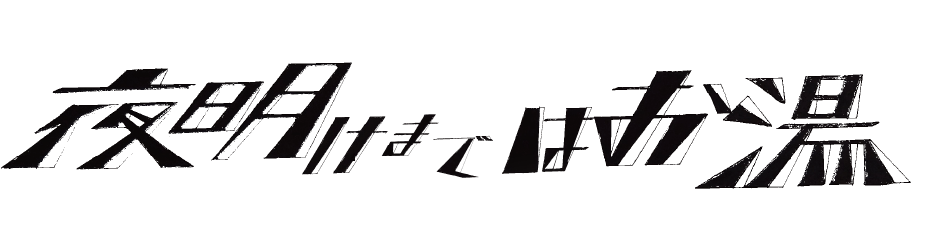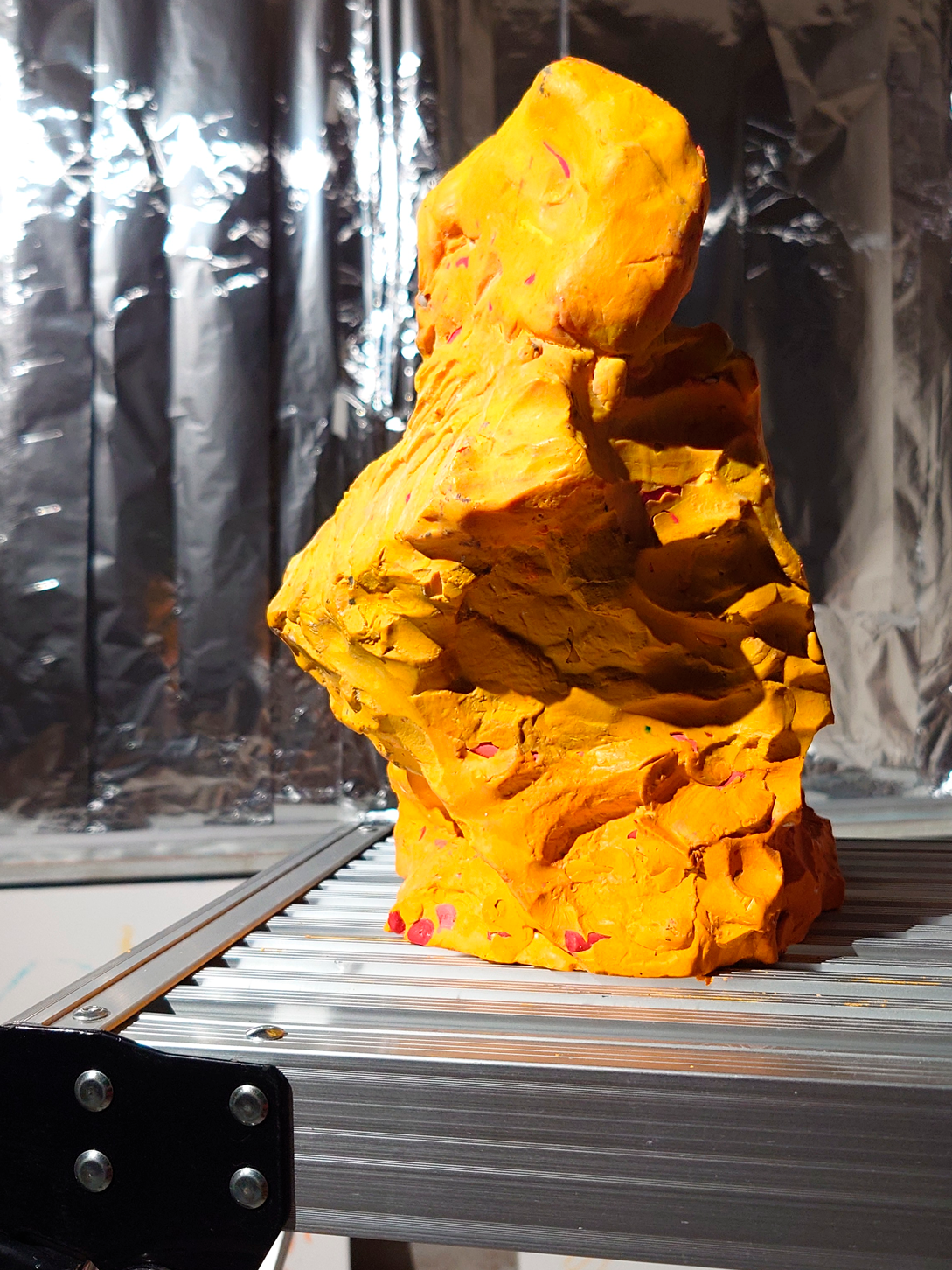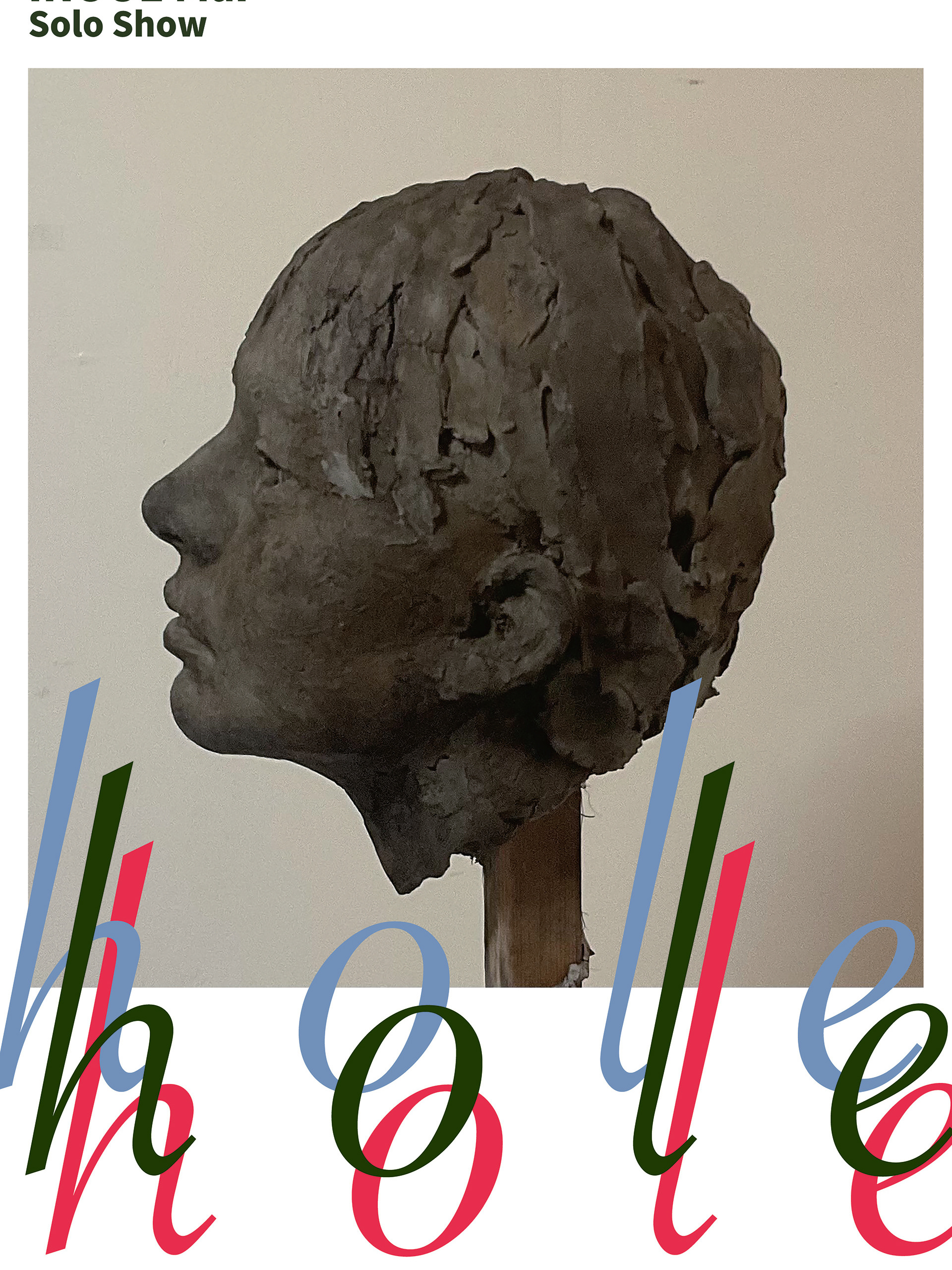2024/9/22に小峰ひずみ『悪口論』刊行記念座談会を開催しました。
2024年夏に発売された『悪口論 脅しと嘲笑に対抗する技術』は、小峰さんが社会運動に関わりつつ、そこで感じたことをありのままに書かれ、かつ、そこに批評的な分析を加えた作品です。関西圏で社会運動を引っ張っておられるかわすみかずみさんと上原さんをお招きして、本書についてアレコレ好き勝手お話ししていただき、観客の方との質疑応答も行いました。
ページ下部に動画の書き起こしを掲載しています。かなり長いですが、ぜひご覧ください。
『悪口論』の虚実を暴く書き起こし
≪目次≫
本編
1.自己紹介と『悪口論』の感想
2.運動に入ってみたら……
3.警官に囲まれて……G7サミットの場面
4.運動から出る言葉
5.誰もが通る葛藤
6.運動のひと工夫、ふた工夫
7.『悪口論』企画の経緯
8.運動の「カッコよさ」
9.ジャーナリズムをほめる
10.悪口論にタイトルを付けるなら
2.運動に入ってみたら……
3.警官に囲まれて……G7サミットの場面
4.運動から出る言葉
5.誰もが通る葛藤
6.運動のひと工夫、ふた工夫
7.『悪口論』企画の経緯
8.運動の「カッコよさ」
9.ジャーナリズムをほめる
10.悪口論にタイトルを付けるなら
質疑応答
1.理論と現場
2.罵倒と差別と悪口
3.自己啓発本としての『悪口論』
4.VOLとロスジェネの間で
5.「バカでけっこう」(?)
6.社会運動を継続する理由
2.罵倒と差別と悪口
3.自己啓発本としての『悪口論』
4.VOLとロスジェネの間で
5.「バカでけっこう」(?)
6.社会運動を継続する理由
**************
本編
1.自己紹介と『悪口論』の感想
〇小峰 みなさんこんにちは。今日は「『悪口論』の虚実を暴く」というイベントをやらせて頂きます。この本の著者の小峰ひずみです。今日は関西圏で社会運動を引っ張っておられるお二方をお招きして、『悪口論』について感想をお聞きし、その後、議論をさせていただければと思います。よろしくお願いします。
〇かわすみ かわすみかずみといいます。そもそも私は、今ご紹介頂いたような「社会運動を引っ張っていっている」わけでは全然なくて、むしろ引っ張られている感じです。社会運動に関わったきっかけはコロナですね。自分が非正規労働者をやっていて、コロナで仕事を失いまして、それで生活補償の運動を始めて、その後に人民新聞社(大阪にある新聞社)で記事を書くようになりました。 取材や記事は、運動関係を中心に、自分も運動に関わりながら書いているという状況です。
〇上原 上原と申します。私も社会運動を引っ張っているというよりは、最近は関わってない(笑)。ただ、4〜5年前から主に関西の野宿者支援の活動をやったり、あるいはそれ以外にデモや集会に参加したり企画したりしました。小峰さんと知り合ったのは、釜ヶ崎だったと思います。
〇小峰
お二人とも今日はどうぞよろしくお願いします。
で、さっそく『悪口論』なのですが、この本は、前半が社会運動に関わるまでの僕の半生なんですね。小学生時代から始まって、大学に入って、その後、社会運動にちょっとずつ関わっていくようになるまでの話をしています。
中盤から後半が悪口に関する分析です。どんな職場でも悪口みたいなものはあると思うんですけど、そもそも悪口とは敵と味方を区別するものです。敵と味方に分けるというのが政治の原理だとカール・シュミットが言っていて、それは政治運動の現場だけじゃなくて職場でもどこにでもある。運動の場でもある。そういう悪口というのをベースに政治を考えたら面白いんじゃないかと思って書いた本なんですね。
じゃあ、『悪口論』を読まれた感想とかをおふたりにお聞きしていいですか?
〇かわすみ はい、私はまず、この本を運動論や戦術論というよりも、私小説として読みました。それから、運動の場で語られた方がいいけど語られてないことをえぐり出す感じがして、けっこう自分の中もえぐられる感じがありました。それはちょっと痛みもあるけど心地いいみたいな部分もあったなあという感じもしてるんです。わりと表現が過激な部分や断定的な部分もあって、人によっては反感を持つかもしれないなあという感じがして、その危うさみたいなものも感じました。
〇小峰 ありがとうございます。じゃあ、ひのさんお願いします。
〇上原 はい、まず1つは、言葉の問題だけじゃなくて、活動家の動作や動きというもの――多分活動家でさえも意識せずにやっていること、なかなか見えていないもの――を、小峰さんなりに運動に関わりつつ、すごく上手く取り出して提示している。そこが印象に残りました。
もう1つは、「技術」という問題を考えるという大事な視点がこの本にある。この本の中で繰り返し「自然」という表現を使っているじゃないですか? 自然の法則にただ身を任せるんじゃなくて、その中にありつつも、それを認識して、応用するということを強調されておられる。最近の私の関心で言うと、社会運動内でのハラスメントの問題に関わる話かなとも思っています。 社会運動は、正しい思想なり正しい理論があってやっている。だから、その中で起きる問題に閉ざしてしまうという傾向があると思っています。どんなに正しい理論があっても、それでも「自然」にハラスメントは起きてしまう。うまく言えないのですが、その辺の問題が「技術」の問題と被るんじゃないか、と思いました。主にこの2つが感想ですね。
〇小峰 ありがとうございます。じゃあ、いただいた感想をベースにして議論をしていきたいと思います。まず、かわすみさんの方で、えぐられるって(言ってましたが)、どこら辺でえぐられましたか?
2.運動に入ってみたら……
〇かわすみ あの、自分の中にも痛みがあるんですね。私は運動に理論を持って入ってきたわけではないので、理論を知らないがゆえの失敗もいっぱいしている。そういう意味で自分も失敗はいっぱいあったなあ、と反省や痛みがあるんですね。
〇小峰 なるほどね。もうちょっと聞いてもいいですか? 喋れる範囲でいいのですが、失敗とはなんですか ? 理論を持ってなかった故におかしてしまった失敗とは?
〇かわすみ 例えば、そうだなあ……まず私は運動に入って参加している人たちがいろんな考えを持っていることそのものを知らなかったわけです。私は元々マルクスとかレーニンとか全然知らなかった。ただ、仕事がなくなって苦しくなった。自分が苦しいと思っていることがあるので、仲間と一緒に「改善してほしい」という運動を大阪市にやっていった。運動の世界に入って来たときに何にも知らない状態だったから、例えばアナキズム的な考えをする人の考えがよくわからないんです。「え? 何言ってんの? 」みたいになっちゃう。例えば、組織論です。私は普通に仕事をしてきただけなので、普通に組織があったんですよ。アナキストの人達は、組織そのものをあまり作らない。そこの部分で対立した。そこでいろんな人と話をして、「あ、アナキズムってあるのか」と理解できるようになった。
それから、1つ大きな目的があると、その中で小さい問題があっても、「そこは目をつぶろうじゃん」という人がけっこういた。そこはよく闘いましたね。具体的に言うと、カジノの反対署名の会で、私が自分の住んでいる区の代表をやってたんですよね。その時に全体のトップの人に「うちの区で集会があるから宣伝をしてほしい」とお願いしたんです。そしたら「ちょっと手が回んないから自分でやってください」と言われた。だから、自分でやろうかなと思っていたら、そのライングループで、他の区の宣伝がわーっと出てきた。「え? じゃあなんでうちだけやってくんないんですか?」とすごい怒ってケンカになったんです。そのとき(地域の)副代表やっていた人が、「お前誰と闘ってんねん。闘うべきは大阪市やろ、大阪府やろ!なんで今ここで闘わなあかんねん」と言ってきた。そこで対立した。
〇小峰 生々しいですね。ひの(上原 以下略)さんも僕も、アナキズム系グループや運動体に入っていると思うんですけど、どうですか? はじめはそういう空間は慣れなかったと思いますが。
〇上原 僕は思想的にはマルクス主義者だと思っているんですけれども、行動的にはアナキズムだと人に言われる。要するに、私は他人との協調性がないんで、他人と何かやるというときにいつも失敗してしまうんですね。
その点について、この本との関連で思ったことを言ってもいいですか? 第4章の「言行論」。シェアハウスの部分で小峰さんが自分の体験を振り返って、人間関係の作り方の型として3つあると言っておられます。
〇小峰 そうですね。アソシエーション・コミュニティ・ネットワークの3つです。アソシエーションは理念や目的を共有する結社のことです。カジノ反対署名の団体だったら、カジノ反対署名を集めるという目的を持ったアソシエーションです。コミュニティは、一緒に住んでたりとか、同じ学校に通っている人がなんとなく集まる集団のこと。ネットワークは友達のことですね。遠方にいても、北海道にいようが、アメリカにいようがどこにいようがつながってはいるわけです。
〇上原 社会運動に関わるとき、私個人は理念や目的の一致を重視しています。とはいえ、長期的な展望を共有できる仲間はそうそういないので、さしあたりいつもプロジェクトというか、この運動現場における理念や期間限定の理念を共有しています。
要するに、運動に誘うことや、いわゆるオルグ(組織化)することによって集まる人というのは、単純に繋がりを求めてくる人が多い。いわゆる生きづらさを抱えた方とかがけっこう来たりする。そういう人たちが自分の生きづらさを社会問題・社会変革と結びつけてくる。それは悪くないんですけれども、他方で、そういった生きづらさを抱える方が、人と繋がりたいという思いがすごく強く出ていて、結局トラブルになってしまったりするというパターンがあります。
〇小峰 なるほど。それはアナキズム系ではよくあることだけれども、一般の組織の中ではそういうことは起こらないんだろうと。弾かれるから。
〇上原 結果として弾かれてしまうんじゃないでしょうか。
〇小峰 アナキズムの話をすると、僕は前作(『平成転向論』)で「党が大事なんや」みたいな話をしてて、いろんな人から「えー?」と言われたんですけど、『悪口論』では「党」の存在をもっと明らかにして、「技術共同体が大事なんだ」と主張しています。「技術共同体」では、デモのやり方とか、記者会見のやり方とか、規制の突破の仕方とか、逮捕されたときの云々とか、救援のときの云々とかをちゃんと共有する。そういう知識の伝承や共有が大切だ、と。
そこで「活動家は技術者なんだ」という命題が出てくるんですね。活動家には活動家の暗黙知がある。活動家には活動家の言語や暗黙知があるから、それを公衆に対してしっかり主張していかないと、「なんかよくわかんない奴ら」「単に騒いでる奴やろ」と見られる。しかし、実はそうではないというところが『悪口論』で、公衆に向かって言っていることなんですよ。リベラル派の言論人にも、活動家を「行き過ぎた権利運動」「過激派」と言ってくる奴がいる。それに対して、「そうじゃなくて、そういう見方じゃなくて」と主張したいという思いがあった。その活動家のネットワークみたいなものを技術共同体と呼ぼう、と。この技術共同体があるから、後輩ができる。その技術の受け渡しで後輩が再生産されるんだという話をしています。だから、代表のある組織ではなく人格の連合体であるアナキズムにかなり近いんですね。
で、次もうちょっと話聞きますね。えーと、『悪口論』の中には、ひのさんが、実は出てくるんですよね。(笑)
3.警官に囲まれて……G7サミットの場面
〇上原 そうですね。出てきてますね。
〇小峰 チョーカッコよく描いた。広島のG7サミット反対運動を起こしたときに、私はひのさんと一緒に行動してたんですよ。他に3人いて計5人くらいでした。で、デモが終わった後に路上を歩いていたら、警官30人くらいに囲まれたんですね。そのときを描いた場面が『悪口論』(38頁~39頁・49頁~50頁)にはある。ある活動家がベンチの上に立って抵抗したというシーンがあって、その活動家がひのさん。けっこういい感じに見えたので、いい感じに書いたんですけど、実際どうでした? 自分としては、見えない・見えてない動作を取り出したつもりなんですが。
〇上原 一連の過程の説明をしたいんですけど。
〇小峰 はい、お願いします。
〇上原 去年の何月だったかな? G7サミットは。
〇小峰 ちょっと覚えてないなあ。
〇上原 まあ、暑い時期ですね。
〇小峰 そうですね。去年の 夏頃。
〇上原 去年の夏頃に、G7サミットがあるということで関西の友人たちと抗議に行ったんです。それが、G7サミット反対に参加するきっかけでした。そして、知り合いの市民団体が集会をやるので、合流するために市内を散策した後に集会の場所に向かっていたんですね。
G7サミット開催期間中の広島では、名目上テロ対策として、街中に機動隊のバスがたくさん停められていたり、警察官がたくさんいました。私たちはあんまり考えずに拡声器をむき出しで持っていた。拡声器をむき出しに持っていたら警察から目をつけられるだろうというのは、後から思えば「そりゃそうだろ」という話なのですが、そのときは思い浮かばなかった。 すると、案の定、警察官に声をかけられたのですが、別に身分を明かしたりする義務はないので断り、振り切った。振り切ったと思ってまたしばらく歩いて行った。そうすると、警察官が30人くらいぞろぞろぞろぞろ後ろから来て、私たち囲まれてしまったんですね。植え込みかなんかの近くですかねぇ?
〇小峰 そうですね。
〇上原 そういう中で「なんで拡声器を持っているんだ」とか「そもそもどこに向かっているんだ」とか「あなたたちは誰ですか」という質問を警察官がしてきた。圧迫をしてきたわけですね。で、この本にもうまく書いてあるんですが、私たちは塊でいたんですけれども、1人づつ囲むような感じで、私たちを孤立させようとしてきた。そこで、「これはマズイな」と思ったんです。そもそも全体を見渡せず警察官が何人くらいいるかがわからなかったんで、あまり考えずにベンチの上に駆け上がった。他にもう一つ主な目的として、市民運動の集会の場所にいる人たちに、僕たちが「遅刻する」ことを伝えたかったんです。ただ電話のやり取りを横にいる警察官に聞かれるのが嫌だったので、ちょっと高いところに登ったというのがありました。
〇小峰 あ、そういうことだったのね、なるほど。
〇上原 はい。
〇小峰 かなりとっさにやったという形だったということですね。
〇上原 そうですね。
〇小峰 まあ、僕が明確に覚えてるのは、そのときに、ひのさんが(警察官の)リーダーに「あんたら結局何したいねん?」という話をしていたんです。
任意やからこっちが別に何か言う必要も見せる必要もない。俺が「行かせろよ!」と言ったら、5〜6人でチョイチョイチョイチョイみたいな感じでこう(両腕を広げる動作をする)壁を作ってきて、「抜け出すのは無理や」となった。「あー、どうすんの」みたいな気持ちでしたね。もうね、30分か40分か、1時間ぐらいやってました。
で、「結局お前らどうしたいんや」という話をひのさんが言うと、警官のリーダーが「この区域から出ていけ」と言った。そこが妥協点です。もちろん、たまたまそうなっただけで、これで事態が打開するとは思っていなかった。
〇上原 ええ、ええ。全く思っていなかった。
それとの関係でいうと、この本にも書いてあるように、結局このあと区域外に出て、各自でまた集会所に向かう。これも余談なんですけど、拡声器を持っていた友達が、「なんで拡声器をむき出しで(自分に)持たせたんだ」と、僕にすごい不信感ぶつけてきたんです。区域の外に出たところで、すごいギスギスしてしまった。
拡声器をむき出しで持ったらまずいので、それを隠すためにビニール袋を買いにいこうってことで、小峰さんが近くのスーパーに買いに行ってくださった。この本にも書いてある「高いビニール袋」を買いに行った。
〇小峰 1210円のね。
〇上原 その間に一緒にいた人に「なんで拡声器むき出しで、持たせたんだ」と怒られたんですね。僕からすれば別に、「みんなバカじゃん」という話で。
〇小峰 アハハハハハ。
〇上原 私にだけ責任をと言われてもという話なんですけれども。あと、そのとき何人かでいた仲間の警察への対応の仕方、バラバラだったじゃないですか。
〇小峰 そうでしたね。
〇上原 そういうのも含めて、これはちょっとマズイなと思ったので、夜に宿泊する場所で総括会議をした。
〇小峰 そう!やりましたね。
〇上原 ダメなところをみんなで確認しようという会議をやったわけです。今思えば、その経験は、『悪口論』で書いてある「信頼と不信」 の構築にあたるのかなと思いました。
〇小峰 僕の方から付け加えておくと、この本は2つの感情の軸が書いてあります。「恐怖と安堵」と「信頼と不信」の2つ。一般的には、「恐怖」「不信」というのはマイナスの感情だからダメで、他方に、「安堵」「信頼」というのはプラスの感情だからいい、と言われています。僕はそうは捉えませんでした。「恐怖」と対になっているのが「安堵」で、この軸はダメ。「不信」の対になっているのが「信頼」。この軸はいい方。なぜ、このような分け方をしたのか。その理由は、信頼関係で成り立つのが運動だからです。運動においては、不信感がどうしても出てくる。だから、互いに抱える不信感について話し合えるという状況になることによって初めて、「あ、私たちは不信感を話し合えるんだな」という信頼関係ができるという話をしてます。
そこで話を戻すと、警官との揉み合いの後の総括会議は、そういう風な経験としては確かにあるかな、と言われてみれば思います。あのときの警察対応はほんとにバラバラで。ある人とか走ってひとりで逃げていきましたからねえ。
〇かわすみ ハハハハハハ。
〇上原 警察官も走って追いかけてましたね。
〇小峰 いやねえ、もう、アホなんかなという。
〇上原 普通にそれは、けっこう危険な行為ですけどね。警察官は、暴れたとかいろいろ理由つけて、逃げた人に関しては、追っかけて圧迫するんです。地面に押さえつける。それで死亡事件がいくつも起きているくらいなんです。非常に危なかったと思います。
〇小峰 その総括会議のときにね、僕も「団結が力なんだよ」と言いました。ひとりで逃げちゃだめだ、と。それが『悪口論』に活きていて、「団結は力だ」という原則を繰り返さなきゃいけないという命題になっている。警官がひとりひとり孤立させようとしていることを思い出して、「団結が力だよ」という原則を強調しないとな、と思ったんです。その仲間はめっちゃいいやつで面白いやつなんですけど、ひとりでバーっと走って逃げた。「いやいやいや、俺ら犠牲にすんなよ」みたいな(笑)。そういうすげぇマヌケな話ばっかり。
まあ、警察官に囲まれること自体みんな慣れてない。屈強な男たちに囲まれることって、20年間生きててあまりないんですよね、社会運動や暴走族に参加しない限り。だからみんなわけがわかってない状態でやらないといけないことが問題かなと思います。そういう状態は変えていくべきやったかもしれんな、と思って、拙い経験を書きました。
〇上原 ちょっと言っていいですか? さっき言った総括会議の関連でいうと、やっぱり信頼関係を取り戻すために会議をしようじゃないかと話をしたんですけれども、その進め方というのも難しいなという思いがありました。ある人からは、拡声器をむき出しに持たせたのは、なぜか私の責任になっている。私はそうとは思わなかったんですけれども、そこで「いや、お前の判断だろ」とは言い返さずに、一応最初は私が泥をかぶって、別にリーダーでもなんでもないんですけれども、私が「情報共有・警察対応の予想で甘かったんです」と自己批判というか謝罪してから(一同 笑)、 会議をみんなでやった。だからこそ、「でもみんなでその誤りを共有しようじゃないか」という雰囲気になった。そこはなかなか難しいなと思いました。
〇小峰 そうですね。いや、ほんとに68年の運動の頃は総括会議がいっぱいあったと思うんですよね。総括会議をしないといけないような状況がいっぱいあって、そういう中で、徐々に人間関係が煮詰まっていくのかなとは思いました。でもまあ、総括会議の経験も必要ですね。
〇上原 そうですね。
4.運動から出る言葉
〇小峰 かわすみさんありますか?
〇かわすみ 私が思い出したのは、一昨年だったかな? 広島の8月6日の平和記念式典に首相が来るので、その抗議行動に参加したんですけど、その前の年までずっとコロナで抗議行動がなくなってたんです。で、久しぶりだから出発する前に計画を立てたんですよ。最初にふたり偵察隊を出して、警察の状況がどんな様子かを見て回り、「ここはこうだった、ここがこうだった」と報告した。その後に、「じゃあこういう風にいこう」と計画をして抗議行動をやったんです。このときは式典の真ん前まで行けたんですね。前はそういう偵察活動がなくて、右翼の人とバチバチになって、気がついたら式典が終わっていたという話はしていました。やっぱり技術論の共有はすごい大事なんだなと思います。それから出発する前にはQカードを作ったりとか、逮捕者の救援対策どうするのかというのを話し合ったりとか。
〇小峰 Qカードというのは、「捕まったときにここに連絡して」などの情報が書かれたカードですね。それを事前に集めとくんですよ。捕まった場合に、「捕まったからここに連絡しよう」ということになるんです。
〇かわすみ 急に逮捕されたりしたら、ワーッとパニックになるじゃないですか。で、警察署の中で尋問になったときに、フワ~っとなっちゃうだろうなと思う。自分もそうなるだろうなと思った。 人民新聞社に務めて何年か経ったときに「そろそろ救援の本読んどいた方がいいよ」と言われました。
〇小峰 ハハハハハ。 救援ノートは、逮捕されたときにどうしたらいいですか?ということが書いてあるこれくらいの薄い本です。それ、読んどいた方がいいということですかね。
〇観客A これ(救援ノートを見せる)
小峰 常に持ってるんですか?すごいですね。
〇観客A 常に持つ
〇小峰 こういう議論、こういう風な言葉の広がりがある。それって言論や論壇からはどんどん駆逐されていってる。Qカードとか、総括とか、救対とか、こういう言葉の土壌から生まれた思考というのは、本当に限られてます。ゼロ年代くらいまでは残ってたっぽいんですけど、それがなくなってたので、『悪口論』を書いたし、書かざるを得なかった。ゼロ年代までは、酒井隆史や矢部史郎などラディカルな言論の地位があった。VOLという雑誌があったりして。そういうのがなくなっちゃってるんで、どうしようかなというのが、『悪口論』を書いた動機のひとつです。
ところで、「『悪口論』はけっこう断定が多くて危うい」とかわすみさんが言ってましたけど、どうですか?
5.誰もが通る葛藤
〇かわすみ そうですね。活動家は究極的には死ななきゃならないとか、
〇小峰 「(生き)恥論」という章にそういうことが書かれています。加藤智大(ともひろ)という人が、秋葉原で連続殺人事件を起こした。その前に書いた文章があって。いま読みますね。
「勝ち組はみんな死んでしまえ
そしたら、日本には俺しか残らないか
あはは
俺がなにか事件を起こしたら、みんな、『まさかあいつが』と言うんだろ
『いつかやると思ってた』そんなコメントする奴がいたら、そいつは理解者だったかもしれない
まあ、お前らは幸せだからな
なんで幸せかって、さぞかし努力されたんでしょうね
で、俺が努力してないと言うんだろ
はい、してません
これで満足かよリア充ども
お腹すいた」
僕、けっこういい文章やなあと思ったんです。これで結局人を殺したんですけど、でも、引用する価値のある文章だなと思うんです。
そこで考えたのは、結局、反資本主義・反近代を掲げる活動家は、今、社会は近代的な私的所有権を前提とした資本主義で成り立っているので、「反」とか言ってもそこで生きてるから存在と発話というか、言語と行為が矛盾する、という問題です。つまり、「そういうんだったらお前、山行けや!山行って時給自足せえよ!」みたいな話になる。それを1回くらい考えません?
〇かわすみ 考えました。
〇小峰 考えましたよね。「矛盾してるんじゃないか」という話になるんですけど、同じように、資本主義は格差の社会で、結局勝ち組と負け組の明らかな違いが生まれる。加藤智大は、「お前ら全員勝ち組だ。俺以外全員勝ち組や」ということを言ってるんですね。それは要するに、(加藤智大以外の人は)資本主義の中で勝ち組として生き残ってて、加藤智大は負け組で、最後の最後まで負け組だったと主張されている。じゃあ、活動家は?ていうか、活動をやっていく人間は?反資本主義、反近代に生きる人間は?と問いを突き詰めていくと、「勝ち組に乗ってていいのか?」という話が出てくると思うんですよね。
しかし、究極の負け組というのは自殺であり、死であると僕は思ってて、でも、僕は死にたくない。じゃあ、どうしようかみたいな話になる。そういう中で、本書の中心的な命題として「活動家というのは勝ち組であることを恥とし、負け組であることを誉れとする」という言葉が出てくる。要するに、「活動家というのは、現実的には死なないといけない存在なんだ。存在と発話を一致させるには、死ぬしかないんだ」という話が、第三章に書いてあります。でも生きたいでしょ、と。ならば、その生は恥でしかない。ここは一番なんかこう、前にかわすみさんが個人的な会話で言っていたことですが、「これは誰でも通る道だ」と。反資本主義、反近代活動家は、誰でもここを通ったんだ、というところですね。
〇かわすみ 私は通ると思っていたんですけど、ごめんなさい、違いました?
〇上原 活動家が欺瞞を生きざるを得ない。そういう問題ですよね。やっぱりある程度社会運動やっていると、普通は孤立するじゃないですか、なかなか仲間ができないので。「俺はこれだけ頑張っているのに、なんでこうなんだ」という問題が出てくる。そして、他人に対しても、「自分の時間なりなんなりを削って頑張るべきだ」という考え方になってしまう。そういう問題も、けっこうかぶっているのかなと思いました。
〇小峰 その、死ななアカンなと、思いました?思ってない?
〇上原 私は基本思っています。
社会運動って、なんだかんだリスクはあるし、コストはかかるし、金にならないというのがある。それでもやっぱりそれを削ってやんなきゃいけない部分が絶対にあるわけです。うーん、かといって、それを他人に求めたりしだすと、それはいびつな構造をもたらすという意味での二律背反が、欺瞞(ぎまん)を生きざるを得ない状況なのかなと思とます。
〇小峰 ほんと、そうなんですよね。結局そこで大変になる。大変というのは、考えることを強いられることが多くなる、という意味です。
もう一回戻りますけど、断定とかが危ういなあと思ったのはそういうところにですか?
〇かわすみ 私は観点が違うかもしれないんですけど、公務員やってて、そういう活動してる人とかって、例えばパートナーがすごく安定した収入持ってて、本人は活動してるという人もいます。
で、活動やってると、「そういう人は本当に活動家なのか?」という意見も、私の周りではあります。そういう中で「自分はどうするのか」と迫られる。「活動一本でやっていくのか」、と。いろんな選択肢があって、そういう中でいろんな迷いがありますね。何かやっていかなきゃと思う。やっぱり何かを見いだしつつある。今の自分は、そこの迷いの中で、でもやっぱり何かやりたいみたいな思いがあるんです。
〇小峰 パートナーはしっかりしてて、自分は活動やってるというのは、ありがちな構図ですよね。韓国って徴兵拒否すると、社会からパージされるんで、まともな職には就けない。だから、選択を迫られると思うんですね。そこでパートナーに正職についてもらって、自分はまともな職じゃないけど自分を貫く、そういう人もいると思うし、それは社会構造的に強いられている。そういう人が活動家ではないという言説は、僕は間違っていると思います。
〇かわすみ こういう意見もあるというのを聞いただけですので、いろんな意見があって、そう思わない人もいると思います。ただ、活動家として、どういう選択をしていくかは問われる。活動家って、往々にしてお金稼ぐのがあんまり上手じゃない人が多いというか、少なくとも、私の周りの人たちはあんまりお金にこだわりなくやっている人が多い。だけど活動にはお金を使うし、その葛藤はすごくあります。
〇小峰 ひのさんどうですか?断定が危ういなという。
〇上原 私はそこまで断定とは思わなかったですね。
〇小峰 たとえば、典型的なのは「庶民は、本書を、読むことしかできない」という最後の一文かな。あの、なんか、 グッとなる。というか、私が読者をグッて刺そうと思っている。「この本はマニュアル本です」と書かれてて、「マニュアル本なんで、活動やってる人間はみんな、この本の批判が書けます。だから、あなたは書くべきなんです」と迫っている。これは自分への宿題でもあります。
最後の文章は「活動家」と「庶民」と2種類の人間に(人々を)分けている。「庶民」とはのうのうと、言い換えれば、勝ち組であることを誉れとして生きている人。自分は恵まれてるとなったらようようと勝ち組の方に行って、対して、恵まれてなかったら鬱々と負け組の方に行く。そういう運命付けられた闘いをしている人たちのことを「庶民」と呼んだ。対して、活動家は「私たちは違う闘いをするんだ」と主張する人のことを指す。そういう人はこの本の批判が書けると、最後に書いた。このラストは周囲359度くらいにケンカ売るつもりで書いてます。あとの1%誰?みたいな話なんですけど(笑)
〇上原 まあ、断定調はあれかもしれないですけれども、この本の性格というものを考えると、別に断定は気にならない優しさみたいなのがあるのかなと。
〇小峰 あー、良かった良かった。
〇上原 やっぱり左翼でものを書く人、何かを言う人って、素晴らしい理念を語るわけじゃないですか。理念を語ったり、「かくかくしかじかであるべきだ、若者は立ち上がろう」と主張する。最近だとジェネレーションレフトですね。「若い世代が立ち上がっている」だとかそういうもの。あの、社会運動の中で起きるリスクの問題には全く触れていない。
私が個人的に尊敬している宮本綾さんという社会運動やフェミニズムに関して発言している方がいるんですけれども、その人が一時期、白井聡という評論家を批判していました。「今の若者はユニクロで試しに働いて、資本主義の酷さを味わうべきだ」と白井さんが言っていて、宮本綾さんはそれを批判していた。「無責任な左翼じゃないか」「若者がそれで試しに入って、身体とか壊したらどう責任を取れるのか」と。小峰さんの本というのは、宮本さんの批判の視点と繋がっているところがあるなあと思います。
社会運動というのはその中で、この本では悪口もろもろ、要するに政治というものがもたらす不信などを捉えた上で、その政治の作用をいかに解毒するかをちゃんと述べていた。それが技術論なのかなと思います。ただ理念を上から述べているだけではない視点から語っている。そういう面では僕はすごく優しさがある本だと思います。
〇小峰 あー、ありがとうございます。
〇上原 そこはやっぱり違う。だから、後半の断定調というのも、それを考えると気にならないのかなと思いましたね。
〇小峰 ありがとうございます。うれしいですね。ちょっと似た話があって、noteでこの本にキレてる人がいるんですね。「負け組が社会を変えるなんてあり得ないだろ」「一体何を思い上がっとるんだ、お前は」と批判されたのですが、でも、最後に「まあでも、わかるところもそれなりにあった」という話が出てくるんです(笑)。だから、わりと普遍的な本だと思います。
6.運動のひと工夫、ふた工夫
〇小峰 別のテーマに移りましょうか。技術と自然の話、ハラスメントの話です。これはひのさんが言ってくれましたが、もうちょっとお伺いしていいですか?
〇上原 社会運動においては「新しい社会を目指していくべきだ」とか「素晴らしい理念があるんだ」という言説がすごく先行しています。他方、その中で起きるリスクや危険性(具体的に言ってしまえば、大義を掲げていても、運動の中ではハラスメントが起きる。あるいは、外在的な問題ですけれども、公安に目をつけられるようなことがすごくあって、人の健康も害すし、ときには自殺しちゃう人もいます。社会運動の内部でさえ政治力学が働いて、人を痛めつけたりもする。それで『悪口論』は解毒剤を出したのかなと思うんです。やっぱり今、主流の左翼の人たちが言ってることって、その部分がないですよね。
〇小峰 昔の人はいました?そういう解毒剤みたいな人。
〇上原 傍流の人がそれを言うことが多いんじゃないかな。昔、向井孝というアナキスト詩人がいました。1910年代から20年代生まれで、イラク反戦くらいまでは生きていて、名古屋や兵庫で活動していた詩人の方です。
その人は「社会運動というのは、ただやるんじゃなくてやり方の方が大事だ」という技術論を強調していました。それでやっぱり高い理念とか目標というものを持っていても、結局それを目的化して活動してしまう。そういう事態に対して、向井は「無理に面白くしようとか思わなくていいから、常にひと工夫すべきだ」と強調している。そこが新しい視点を提示している方だと思うんですけれど。
〇小峰 向井孝の工夫は何だったんですか?
〇上原 なんだっけな?例えば、ビラの文体や呼びかけ方を試しに変えてみるとか。
〇小峰 なるほど。確かにそうですね。それは僕もそう思いますね。やっぱり素人の乱
(東京・高円寺を中心とした運動団体)は、ひと工夫ふた工夫がすごいってことなんですよね。外山恒一とかも、思想はどうあれ、ひと工夫ふた工夫してきた人だと思うんですけど。
〇上原 そうですねえ。確かに僕も、ひと工夫ふた工夫をしないといけないなあと思ってるんですがね。工夫って現場でしか残らないので、おもしろくない。
〇小峰 僕とひのさんとか、僕と共通の友達で、デモの企画をしたことがあるんですよ。で、友達はオーソドックスな動き方もするんですけど、オーソドックスな動き方だけをする人ではない。吉本興業の前で街宣するなどしていた。
〇かわすみ 私もやりました。
〇小峰 最初の頃、けっこう人が集まったんですよね。十数人集まった。今まで社会運動に関ったことがない人も、十数人来たというのは大きい。これはきっと成功だろうなと思うんです。
その友達と、梅田の車道を7人くらいで裏金問題追及デモをしたことがあります。そのときに、その友達は「コールアンドレスポンス」、コールの仕方を工夫していた。そいつは「わっしょいわっしょい」と言っていた。「わっしょいわっしょい」って意味不明なんですよね(笑)。コールとして何を伝えたいかわからない。ただ「わっしょいわっしょい」しか言ってなくて、俺はそれがすごく嫌でした。「何やってんの?と周りから思われるやん」と思ったんです。デモ終了後、「なんでああ言ったん?」と訊いたんですけど、その友達は「盛り上がってるとこを見せないといけない」という意識でやっていたそうです。「沈鬱にやってる、歩いてるだけみたいなのはあかん」「俺は盛り上がってるところを見せたいんや、少人数であってもいいから」と。そのときに「なるほどなるほど、そういう考えか」、と納得しました。
当たり前ですけど、けっこう活動家って人それぞれ違うんですよ。オリジナリティを出したいから、けっこう工夫する人もいるんですよね。手作り感もあって、半分文化財みたいなところがあると思います。なので、「なんでそれをやってるかわかんない」というところもけっこうある。そうしたものは、聞いてみないとわからないでしょ?
それなのに、『悪口論』では『情況』編集長の塩野谷恭輔さんを批判しましたが、言論人は一切見ずに、一切聞かずに「あれはアカン」みたいな話をするんです。いやいや、と。戦略上、戦術上の意図があって、ひと工夫したんですよね。それを簒奪(さんだつ)するのはダメです。上からというか、既存の理論とかによって簒奪するのはちょっとおかしいなという感じがある。この本にも書いてあります。「聞け」と。「活動家の人に聞け」と。「なぜそうしたのかを聞け」と書いてますね。
〇上原 いまのことでちょっと思い出したんですけど、さっき話題に出した向井孝が運動をやることより、やり方が大事だと話していました。なぜやり方が大事かというと、ここ抽象的な言い方なんですけど、やり方を変えることによって、運動内の人間関係が変わるんだと言ってましたね。
同じ社会運動の中でやってる人でも、作法というか、やり方が異なるじゃないですか? 技術を論じることによって、「じゃああなたはなんでこういうことを考えていたんですか?」という議論を丁寧にする機会ができる。そういう意味で運動内部の人間関係が変わるのかなというのは、今思いつきました。
7.『悪口論』企画の経緯
〇小峰 ちょっと脱線しますけど、[2015年の国会前デモの先頭に立った]SEALDs(自由と民主主義のための学生緊急行動)は、ひと工夫ふた工夫あったと思うんですね。僕はSEALDs批判でデビューしています(『平成転向論』)。SEALDsの人たちは「日常に帰る」という話をするんですよね。で、運動体も一律に日常に帰るべきだという話をして、実際解散しているんです。僕としてはすごい違和感があったんで、SEALDsの方針がよくなかったというのを『平成転向論』で批判したんですね。
ついでに言っておくと、この本(『悪口論』)の(出版社の)百万年書房の編集者の北尾修一さんはSEALDsの大ファンで支援者でした。なんかSEALDsのことが好きすぎて、台湾のひまわり運動の人と、香港の雨傘運動の人と、SEALDsを引き合わせてるんですよ。後に、『日本×香港×台湾 若者はあきらめない』として出版されています。北尾さんは、本当にSEALDsが好きで、SEALDsの前身のSASPLの時代の街宣を見て泣いたと言っておられました。
北尾さんはかつて太田出版に在籍していたんですが、太田出版でatプラスという左派系の雑誌がありましたよね。そこで社会学者の上野千鶴子というSEALDsの同伴者と、同じく社会学者の北田暁大(あきひろ)という人が対談したんです。そこで北田さんがSEALDsに批判的なことを言ったんですね。その原稿を構成したのが、当時太田出版の従業員だった綿野恵太さんです(現在は批評家)。そして、綿野さんが同僚の北尾さんにそのゲラを見せたらしいんですよ。すると、北尾さんは「北田というのはけしからん」と「クソバイス(アドバイスのクソバージョンのこと)オジサンや、北田は。SEALDsのクソバイスオジサンや」と激昂したそうです。
その後、SEALDsが解散した後に、「これで良かったんかなあ」ということを北尾さんは思ったらしいです。そこで『平成転向論』を見て、メールを送ってきてくれたんですね。「小峰なあ、お前SEALDs批判するんやったら違う運動論持っとるんやろなあ。お前それ出せよ。クオリティはええからとりあえず出せ」と言われたんです。もちろん、こんな言いかたではないですよ(笑) そして、『悪口論』が出来上がったんですね。
8.運動の「カッコよさ」
〇小峰 みなさんは、SEALDsとかどういう風に見てました?
〇かわすみ 私は、SEALDsが活動していたその時期にはガッツリ仕事をしていて、その状況に全然関与していなかったし、興味もなかった。運動の世界に入ってから、SEALDsの話を聞くようになった。そのときはSEALDsそのものにどこがいいとか悪いとかの評価も何もなかった。だから、私の中で評価とかはないんですけど、私が自分で活動してきた中で思っていることは、やっぱり運動って地道にやっていく以外ないなあと思います。どう考えてもコツコツ地道にずっと続けていく以外ないなと、ほんとに思いましたね。
確かに何ていうの?人目を引くのも大事だし、例えば裾野を広げるとか、もっといろんな人が関われる場を作るってすごく大事だと思います。でも、それとともにコツコツひとつずつやっていくことでしか成し得ないことがあると思います。SEALDsが「普通の人に戻る」とか言うのとか、その言説の中で「非日常」という言い方をしていたのは、私は今の感覚としてはすごく違和感がある。私の中では「非日常」じゃなくって、日常だと思っているというか、みんなの問題だと思っているんです。私だけの問題じゃないから活動、と思っている。だから、そこに「非日常」とか「終わったら戻る」という感覚は、私はあんまり、今の段階ではないです。
ただ、わからないですよ。これから先、私が運動から離脱するかもしれないし、続けるのかもしれない。だから、今言っていることが、「そうだ」と言えないときが来るかもしれないけど、でも、あの、今の時点としてはそう思っているということですね、はい。
〇小峰 ひのさんはどうですか?
〇上原 まず1つ目として、かわすみさんがおっしゃった、運動が終わったら日常に戻るとか、そういうものに違和感がある、というのは私も同じです。社会運動って、結局巻き込まれるという部分が強かったり、あるいは、単純に好きな人がそこにいるからそこにいて、そのままダラダラしてしまって、そのまま抜け出せなくなったりすることが多いと思うんですけれども、そういうのを考えると、そんな日常と非日常を分けられないだろうというのがまず1つ、やっぱりある。
もう1つは、マスメディアの取り上げ方として「若者が頑張っているんだ」という枠組みやフレームを作るということ自体に、すごく違和感があります。結局、僕自身が、野宿者運動とか基本的にはマイナーな人間、かつ、今の社会では見えなかったものとか、見えない人間関係だったり、見えなくさせられている存在と一緒にやっていくことが運動だと思っているので、あそこまですごく可視化されて、既成のメディア、既成の情報流通に乗っかりすぎているというのはどうなんだ、というのは今から思えばすごくあります。当時は僕、中学生だったんで、後付けなんですけどね(笑)。
〇小峰 なるほど。僕は当時大学生4年生だったんで、ちょうどSEALDsのリーダー格だった奥田愛基さんと同じ年です。それで、すごく影響を受けた。影響というか、「こんなんあるんやなあ」と。でも、ちょっと違和感あった。それで、阪大はアナキストの方が多かったんで、アナキスト系の方にいきました。ただ、SEALDsには工夫があったような気もするんです。例えば、のぼり旗全部降ろすとかプラカード統一するとか。その工夫がいいものかどうかはわからないですけど。
僕がよく覚えているのは、安保法制に反対する総がかり行動というデモのことです。いろんな団体がのぼり旗立てて来るんですけど、写真を撮るからみなさん1回のぼり旗降ろして、配られた「アベ政治を許さない」というプラカード――アホみたいな標語のプラカードあったんですね――をみんながあげるということをやった。それがすごいSEALDsっぽい、今風のスペクタクル政治、見せ物政治の典型だったなと思ったことを覚えています。SEALDsは特定秘密保護法があって、安保法制があって、翌年の参議院選挙まで続いていた。結局、スペクタクルで集約した力を、参議院選挙に落とし込んでいった。それはひとつの工夫ではあったんだけど、僕としては違和感があった。ひまわりとか雨傘とSEALDsを並べることは相当な違和感があるというか。ひまわりのときは突入してるんで、実際とめてるんで。雨傘は、かなり身体張った運動なんで。ぜんぶ非暴力直接行動なんですよね。そこがけっこう違うかなという感じがしました。どうですか?
〇上原 私は、さっき言ったアジアの他の運動とSEALDsは意外と共通点もあると思っています。「スター」をつくる。全否定も全肯定も、あれ自体ではできないと思うんですけれども、そういう意味では共通点はあったのかなと思います。
〇かわすみ SEALDsってやっぱり見栄えがすごく良かったし、コールがとても簡潔でわかりやすかった。カッコよかった。やっぱり若い人たちから見たら、本当に単純にカッコいい。そういうところがあるんですね。対して、いわゆる活動家って「カッコいいよね」と言われる場面があんまりない。なさそうじゃないですか?どう考えても。だから、若い人たちが惹きつけられていったのはよくわかるような気がするんです。まあ、そういう部分も持ちつつ、例えばより実質的な戦略をもって何かをやろうとしていくという両方の軸があったら、もっと違った展開があったかもしれないなという気はしています。
〇小峰 しかし、例えばですが、釜ヶ崎で野宿者の追い出しがあったじゃないですか? 夜間、寝てた場所(施設)に柵をつけて、野宿者が入れなくなった。その反対の闘争をやっていたときに、ある日の抗議行動がかなり長引いた。そして、施設側が抗議者の僕たちのことを、何時間もやっているからということで、警察呼んだんですね。で、警察呼んで、結局我々が囲まれて排除されたんです。そのときに、ある女性の方が施設の職員をがん詰めしていました。「あんた、責任取れんのか?柵(を設置)されて生活めちゃくちゃになるじゃないか。お前どんだけのことしてるかわかっとんのか!」ということをバーと言っていました。「ああ、非常に「カッコいい」なあ、ちゃんと怒ってて、これはすごいなあ」という風に感じました。(『悪口論』138頁~140頁)
9.ジャーナリズムをほめる
〇小峰 まだ用意してる質問があるんです。前半にジャーナリスト批判があるんですよね。要するに、世の中にある問題の数なんかはどうでもいいんだと。問題が多くて、あれも問題、これも問題、介護問題、少子化、外交、戦争、云々、云々、云々、云々と言われている。しかし、問題あげられても、萎縮するだけだと、変な話ね。
〇かわすみ その通りです、はい。
〇小峰 問題の数はどうでもよくて、耐えることができるか、その問題の数に耐えることができるかどうかが問題である。つまり、世の中がどうなのかじゃなくて、私たちがどう生きるか、私たちがどう生きたいかが問われてる。他の国がどうとか、どうのこうの、何冊売れようが、そんなのどうでもいいと。これは斎藤幸平への当てつけなんですけど、アメリカがどうとか、お前の本が売れてるとかどうでもええねん。とりあえずどうでもええねん。誰がなんと言おうがどうでもええねん。そんなの関係ないねんという話をしてるんです。
他方で、かわすみさんは人民新聞の記者として、記者会見で吉村とかに質問ぶつけているわけなんで、このジャーナリズム批判をどう思ったか。あるいは、一般的なジャーナリズムと運動の関係についてどう思いますか?
〇かわすみ うんと、どう答えていいかな? まず、一般的にジャーナリズムに対する批判ってあるじゃないですか。「政権寄りのことしか言わない」とか「全然取材してないじゃないか」とか、いっぱいあると思うんですけど、それと分けて考えた方がいいことがあります。大手のジャーナリズムと、フリーなどの大きな資本によらないジャーナリズムとは質が違うんですよ。だからそこのところは分けて考えた方がいいと思といます。
現在はフリーのジャーナリストとか、大きな資本によらない小さな出版社や新聞社とかで、すごくいい仕事しているところがけっこうある。それと、大手新聞の場合は規制が多くて、なかなか書けないことが多い。私の師匠の石塚直人さんという人がいるんですけど、元読売新聞の記者で、定年後に小さい新聞社とかを回っていろんな指導してくださった方なんです。小さい新聞社を応援したい、そうやってちゃんと真実を伝える新聞を応援したいと回っていった。人民新聞にも指導して下さった。それで私も石塚さんから教わって、いろんな勉強をしたんです。石塚さんは元々、関西外語大学の朝鮮語の専攻だったんです。朝鮮学校の問題や夜間中学の問題をずっとライフワークとしてやってきたんですね。
これは私も過去に記事に書いたんですけど、読売新聞に入ったときに、朝鮮関係の記事を書いたら潰されたと言ってました。だから、晩年、「僕は書きたい記事が書けないんだ。読売では書けないんだ」と、ずっと嘆いていたそうです。で、その読売を辞めてから、ネットで発信をするようになって、やっと好きなように書けるようになったという人だったんですね。 で、そういうことを考えたときに、フリーであることがいかに書けるかということですよね。
それともう1つは、今、市民メディアの時代が来ている。自分たちで発信ができるという状況が整ってきている。だから、批判だけではなくて、自分たちで発信していったらいいと思うんですよ、どんどんどんどん。それはすごくやるべきだと思っています。
最後の1つ。ジャーナリズム批判の根幹がどこにあるかということも考える必要があると思っています。例えば私も記者会見でいっつも思うのは、例えば大阪府の知事とか、「メディアがちゃんと取材してないじゃないですか!」と言うじゃないですか。石丸さんもそうだったでしょ?中国新聞をすっごく攻撃したじゃないですか。あれも自分たちを正当化するために批判してることがいっぱいある。橋下さんとかずっとそうでしたよね。攻撃して、自分が攻撃されないようにする。だから、政権とか権力側が、自分たちの都合の悪いことをかわすために、メディアを批判する可能性もあるわけですよね。だから、そこを見極める必要があるのかなという風に思っています。
市民がそこに安易に乗っちゃって、「メディアが悪い、メディアが悪い」と言い過ぎると、やっぱりメディアは萎縮していくし。現場で頑張っている記者はいっぱいいるんですよ。だから、私が現実に大手の記者から聞いたのは、例えば新聞とかに載ってて、この記事がすごくいい記事だ、すごい取材してると思ったら、新聞社に「この記事が良かったです」と投書してほしい、と。そうしたら記者も頑張れる。そういうことが大きくなったら、そういう記事が増えていく。だからそれをやってほしい。
だから、批判をすることももちろん大事。これおかしい、こういうのもっと取材しろとか。それも大事なんだけど、他方で、もう1つの観点として、いい記事を書いている記者を応援してほしいというのはあるんですよね。だからそこはひとつのジャーナリズムとしてはあります。
ジャーナリズムと運動の関係で言うと、私が実際にやってきたことになりますが、例えば、釜ヶ崎の監視カメラ弾圧というのがあるんです。それはえっと、あのー、団結小屋の方に元々、
小峰 団結小屋というのは、釜ヶ崎の野宿者たちを支援、あるいは一緒に生きていくために、活動家や当事者たちがつくったプレハブ拠点ですね(2024年12月の強制執行で解体された)。屋根があって、その下に調理場があって、包丁とか、椅子とか机とか器とか箸とかがある。あいりんセンターの前にあります。
〇かわすみ その団結小屋に、市の職員が監視カメラを向けたことがあった。それでそこにいた人たちが手袋やビニール袋を被せたりしたんです。そのことを市の職員が「犯罪だ」と刑事事件として訴えたんですね。その裁判では、団結小屋の人たちが全面勝利しました。
その後に私が、吉村知事の会見に出て、この事件に関しては住民側が全面勝訴してるということと、それから住民側は知事に謝罪を求めているという話をしたら、知事は「これは刑事事件なので、私が謝る必要はない」と言って突っぱねたんです。
〇小峰 どういうこと?!
〇かわすみ 刑事事件は刑事事件として、それが事件か事件じゃないか、住民側が悪いか悪くないかということの判断なので、知事が謝る必要はないという理屈ですね。
だからそれで、そのことを運動の人たちに、「こんなこと言ってたよ」と伝えたんですね。そしたら運動側の人たちが、「それはおかしい」と言って、また大阪府の方に要請に行ったことがあった。だから、そういう流れというのができつつある。それは他のとこもそうですね。れいわ(新選組)の大石あきこさんとかも、そういう流れを作ってる。市民が大石あきこさんのところに情報を寄せて、大石さんが流していくということをやっている。そういう動きというのは大事かなと思います。
〇小峰 メディアもちゃんとしたフィードバックをしないといけない、育たないという。
〇かわすみ そうですね。双方向のメディアも出てきてますよね。例えば、万博の問題をずっと取り上げてる今井一さんたちがやっている番組も双方向ですよね。市民が情報提供して、こういうことありますよみたいにフィードバックしていく。
〇小峰 フリーは書けるという話なのですが、SNS時代なんでみんな書ける時代じゃないですか。逆にそれによって、暇空茜、トランプ、N国とかも広がる。これらと下部構造的には同じですよね。
〇かわすみ はい、そう、確かに。ネット規制が今全然ないので、もう書きたい放題になっている。だから、私たちが、情報をきちっと見定めていくのがすごく大事です。踊らされずに、事実かどうかをきちっと選ぶ。その上で自分で判断していくことが大事かなと思います。
10.悪口論にタイトルを付けるなら
〇小峰 『悪口論』に別のタイトルつけるなら、どんなタイトルにされますか?またそれはなぜですか?ひのさんどうでしょう?
〇上原 小峰さんもけっこう意識して、この本でも引用されている津村喬っているじゃないですか? 津村喬の『横議横行論』では、常に身振りの問題を扱っているんですね。情報流通のあり方であったり、あるいは身体の動かし方であったり。そこから今の社会とは違うものを目指す。一般社会では、ヒエラルキーに基づいて情報が流れていったり、人間の行為というものも、それに影響を受けているから。
そういう中で、そうではない構築を目指す。そのときに、津村は物事の引用を意識するんですね。そこには、私たちの社会というものが、無数の引用で成り立っているという前提がある。言葉だけじゃない。例えば8時間労働の要求が弾圧されていたときなんて、労働者の団結権とかストライキ権もなかったわけですよね。そういう中で無数の行動によって、今の権利を体言一致で作ってきた。そういう無数の言葉であったり、行動であったりで、今の私たちというのがある。それを改めて過去であったり、あるいは古今東西のいろんな場所から新しく意味を置きなおした上で、別の動き、情報のあり方というのを目指すという点で、この小峰さんの本もそれにすごく近いと思っています。活動家の意識されざるものから引用するという。津村喬は『横議横行論』の後に『続横議横行論』も書いてるんですよね。だから、『続々横議横行論』。
〇小峰 アハハハハハ。
〇上原 仲間と読書会やって思いついたんです、はい。
〇小峰 続々ね。続々、カタカナ?ひらがな?続々はひらがなですか?漢字ですか?
〇上原 漢字で。
〇小峰 かわすみさんどうですか?
〇かわすみ 私、なんかそんなすごい高尚なものが考えつかない。私はどちらかというと
私小説として読んだし、小峰さんの本当にこう、生の感じをすごく大事にした方がいいかなと思ったから、『僕は現場で考えた 哲学と市民運動』。
〇小峰 僕は現場で考えた。なるほど。
〇かわすみ すごいベタでごめんなさい。
〇小峰 いやいや大丈夫です。著名な活動家の園良太さんの『僕が東電前に立ったわけ』みたい。
質疑応答
1.理論と現場
〇観客B かわすみさんが最初に言っていた、理論じゃなくて活動から入ったという話が面白かったです。そのときに、いろいろといざこざがあり大変そうだなと思いました。じゃあ、理論を知っていたら、そういういざこざはなかったのかどうか?理論を知っていたなら避けられたかもしれないということを聞いてみたいです。
〇かわすみ そうですね。理論があったら避けられただろうなということについて、ですね……。活動家は強制性と距離をとるじゃないですか。私はやっぱり運動ではなくて、実際に仕事をずっとしてきて、そっからポンと運動に入ったので、強制性がけっこう強い。で、その部分での衝突はいつもあったかなと思います。具体的には、梅田解放区(梅田HEP前街宣)で誰が来てもしゃべれるというフリートークをやっていたんです。そこで、何年前だったかな、HEPから飛び降りて亡くなった人がいたんです。その後にやった街宣で、私が「みんなでその人のために黙祷しませんか」と提案を出したんです。そしたらある人が「そういうのは強制することじゃない」と言ったんです。そのときに私は、すごい悲しい思いになったんです。「え、なんで、みんなそういう思いないんだ」と、ちょっと悲しい思いになって、「え、みんなで黙祷してあげればいいのに」と思ったんですね。
でも、そこは多分理論があったら超えられたかもなと思います。「あ、そうだよね」と。その提案も多分出さなかったと思います。理論があったら、それは私がやればいいことで、他の人に強制することではないとわかったかもしれない。
2.罵倒と差別と悪口
〇 観客 今回小峰さんの本を初めて読ませていただいたので、感想をお伝えしたいと思います。けっこうすっと読めたんで、一気に読ませていただきました。自分も政治的なことに興味がありつつも、なかなか政治活動に出ない。デモとか行ってるわけでもないし、かといって気に入った政権とかもないんですけれども、「じゃあイデオロギーがないか?」と聞かれたら、「うーん」みたいな感じではある。そんな感じです。
最後の谷川雁と吉本隆明の罵倒の応酬の場面を読んで思ったのは、「なぜ『罵倒論』じゃないんだ」ということです。『悪口論』では悪口を否定的に捉えてるけど、そこから悪口の内部を構造的に抽出して、罵倒に昇化していくという方向は、どういう思いで、書かれたんですか。
〇小峰 悪口というのは普通に悪口。普通に言う、ガス抜きみたいなものです。罵倒というのは、孤立していても「お前たちは間違ってる」と言えるのが罵倒です。逆に言うと、権力者側が新聞記者を罵倒したり、強者が弱者を罵倒したり、弱いものを更に辱めることもあると思う。そういう両義性がある。
ただ、罵倒ってあんまりしないじゃないですか。でも、悪口はみんなすべからく言うので、そのすべからく言う悪口という土壌から政治というものを考えていきたいという気持ちが、『悪口論』というタイトルに込められています。誰にでもある経験から政治を捉える。それが『悪口論』に込められた思いです。
〇観客B 続きです。続きというか感想ですが、やっぱ本文中に「庶民ごときに何が見えるか」の「ごとき」というのは、「身の程を知ってくれ」ということだと受け止めました。「そこからスタートしてくれ」ということだ、と。「あなたはここからやってくれ」と、できるから、と。すごく勇気づけようとしているなと思いました。以上です。
〇観客A 登壇者だけではなく皆さんにお聞きしたいのが、悪口と罵倒とヘイトスピーチはどういう違いがあるのか?
〇小峰 一応この本の中では、悪口というのは悪口じゃないですか。普通に悪口。あいつアカン、キモい、カスや、ガキや、とか。悪口というのはグループ作るんですね。あいつキモいよなあとか、あいつカスやなあという発言は、ある種の申し合わせが前提になっている。「あいつはダメだ」という申し合わせがあって、それを再確認するのが悪口です。だから1つのグループを作るんですけど、そのグループから出て、そのグループ以外の人に対しても、「あいつはカスだ」とか「あいつはキモい」とか「あいつはダメだ」と言うためには、アジテーションというか、みんなの前に立って罵倒する必要がある。グループの外部にまで価値判断を提示するというのが1つある。
それと、ヘイトスピーチは差別の問題、どうですか?
〇かわすみ そうですね。ヘイトスピーチというのは、何ていうのかなあ、個人の尊厳を傷つける領域に入ってしまっているものだと思うんです。それでよく、ヘイトスピーチをやる人の方が、「これは表現の自由だ」という人がけっこういるんだけど、「表現の自由」と、人の権利を侵してまで自由と言えるかというと、私はちょっとどうかなというのがありますね。
私はわりと、朝鮮学校の運動とかに参加したりしてるんですけど、実際にヘイトスピーチされた人いっぱいいるんですよ。その人たちの話を聞くと、やっぱりすごく悲しい思いをしたとか、なんでそんなこと言われなきゃならないんだろうという声がたくさん出てくるんですよね。だから、そういうものはおかしいと思うし、ヘイトスピーチというのは、人の権利や尊厳を侵してまで自己主張する、そのことだという感じがしています。
〇上原 答えにならないかもしれないですけど、ヘイトスピーチって差別の問題じゃないですか。相手を非人間化する。そういう意味では悪口にも差別的な要素は入ったりするので、そういう面では境目というのはいろいろあると思うんです。
この本で扱われてる「罵倒」というのがけっこう重要だと思うんですけれども、「罵倒」は相手を抹殺するのではなくて、むしろ連帯の呼びかけにもなる。そこは違うのかなと思います。差別の問題になると、やっぱり相手を非人間化、抹殺する対象にするという面で違うのかなと思いました。
〇小峰 僕は差別の問題については、標準と非標準とものがあと、その標準の側から、非標準とされている人たちをその非標準とされている要因を指摘して攻撃するという形になることがいけないのかなというか、やってはいけない悪なのかなと思います。
もう1つあと、悪口の話なんですけど、田中美津の差別論が本書の肝の部分で出てきます。田中はウーマン・リブの活動家です。じゃあ、『悪口論』をどうして差別論にしなかったか。『差別論』でなく『悪口論』という形にすることで、男性にも適用できるようにしたんですよ。ある意味、田中美津の立論を男性に適用できるようにした。要するに、日本人のシス男性だったら現在の日本社会では差別とかあんまりされないんですよ。その人間像が日本社会の生産主体であり、標準形なのであんまり差別されることないんですね。ただ、悪口は言われるんです。罵倒はされる。「役立たへん」とかいろいろ言われる。その経験というのを考えるときに、田中美津の差別論を悪口論に変えて、男性にも適用できるように、より間口を広くしたというのがある。だから、実をいうと、差別論が抜け落ちてる。というよりも、あえて抜け落ちさせてるんですね。そっちの方が広く訴えかけてるかなと思ったからなんですけどね。
3.自己啓発本としての『悪口論』
〇上原 質問があります。この本ってハウツー本じゃないですか。いい意味で自己啓発本だと思うんです。自己啓発本は心理学などの法則を認識して、それを応用しましょうという話をする。あるいは、経営者が自分の経験談を法則化する。「私はこうして成功した9つの法則」という感じじゃないですか。
他方、社会運動の場合は成功というものがない。『悪口論』にも吉永剛志さんの「そもそも展望がないのが展望で、道がないのが道だ。それが運動の大前提だ」(46頁)という言葉が引用されていた。そういう意味ではいわゆる安易なビジネススケール的成功とは違うんですけれども、他方で、法則の応用という面では自己啓発本だと思うんですよ。それはすごくいいと思といます。
あと、僕の友人なんかでも、社会運動の中で、まあ、悪口で傷ついて運動離れた人が、実はこの本読んで復帰してる人もいる。
〇小峰 嘘、メッチャ嬉しいやん。そんなことある?
〇上原 僕はそういう意味では、自己啓発本的なものを書くというときに、どうして「私小説」風にしたのか?経営者も自分の経験に則すから、それは普通なんですか?
それと、一昔前だったらVOL系の人が運動の技術を論じていた。でも、そういう人たちの書くものは、ハウツー本とはちょっと違うじゃないですか。自分の経験みたいなのはあまり書かない。そこで、どうしてこういう文体、文体というか、文章になったのかが気になりました。
〇小峰 まずVOL系の話すると、酒井隆史とか、矢部史郎とか、あと栗原康みたいな、90年代に早稲田大学を中心にアナキズム系の運動に参画した人たちがいました。僕はそこに一定の学問的な水準があると思といます。『暴力論』(酒井)とかは名著です。その人たちは、戦術の学術的な価値付けはしたんですよ。ただ、私小説寄りの話はしていないんですね。
それに対して、僕がなぜ私小説風で書こうと思ったかというと、昔、赤木智弘さんが「『丸山眞男』をひっぱたきたい--31歳、フリーター。希望は、戦争。」という論文を出したじゃないですか。赤木さんは自分の実感から政治を語っていました。そういうロスジェネ世代の文体みたいなのを引き受けた上で変えないといけないと思ってたんですね。その流れを赤木智弘さんとか杉田俊介さんとかに任せてはならぬと思といました。『悪口論』でも杉田俊介さんは引用されていますが、もっと闘争の話をしなければならないと思いました。そういう実感ベースで政治を語るということ。あと、単純に酒井隆史みたいな文体で書いても読まれへんやろみたいな気持ちがあった。もう1つは、『悪口論』は百万年書房という出版社から出てるんですが、ここは『暮らし』レーベルを中心にエッセイをたくさん出している出版社なんですね。そのスタイルを真似したという点もあります。
あと、僕が前書いた『平成転向論』というのは「論駁文」なんですよ。「論駁文」というのは、「お前らの方針間違ってるやろ」と主張する文章です。僕はそっちの方が得意なんですけど、論駁って今、なかなか成立しないと思います。今は、なにか批判すると、ゲスの勘ぐりに晒される。つまり、「お前はこの批判や論駁を、承認欲求であったり有名になりたかったり金を稼ぎたかったり、そういう気持ちで書いたんやろ」と見られがちなんですよ。なので、そういうゲスの勘ぐりを一掃する文体が欲しかったんですね。「こんだけやったら文句ないやろ!黙れ!」みたいな感じがね、欲しかったんです。だから、こういう文体にして、この本が刊行されて10年後に、「この本みたいにやってないやないか」と言われる可能性高いけど、まあそれでも仕方がない。そういう「黙れ!」という気持ちがあったという話ですよね。
〇上原 すごくいい答えをもらいました。ありがとうございます。
〇かわすみ いいですか? 私はねえ、この文体が面白かったんですよ、すごくね。面白い文体だなと思って、わりと好きだったんです。前に一度、「田中美津の文章を真似てるんですか?」と小峰さんにお聞きしたことがありますね。
〇小峰 そのときなんて答えました?
〇かわすみ ちょっと影響受けてますと言われてました。
〇小峰 アハハハハハ。田中美津には影響受けてますね。田中美津は幼少期からの自分の経験を書いています。幼少期から受けてきた差別を中心に、すなわち自分をけなすものを中心に文章を構成していく。僕もそれは参考にしました。そうすると、やっぱり田中美津風になるというか。私はこういう風に言われた、で、私はこう思うって、その相手の言葉に対して私はこういう風に跳ね返すという論法をとると、やっぱ田中美津っぽくなる。逆に言うと、田中美津くらいしかそういうの書いてない、そうでもないかな?
〇かわすみ あー、そうかもしれないですね。確かにそうかもしれない。
〇小峰 森崎和江とかもちょっと書いてますけど、やっぱ田中美津は顕著で。上野千鶴子はもっとアカデミシャンっぽい文体とるんですね。
〇かわすみ 小峰さんの感じというのが、すごく出てたんですよ。なんか、言っていいのかな、どう言っていいのかわかんないですけど、そのー、言葉がフワーっといっぱい出てくるような感覚というのか、わーっと「しゃべりたーい」みたいな感覚ってあるじゃないですか。そういう文体。そのままそれが文体に出ている。
それでちょっと思っていたところがあります。よく文章書くときは、理論立てて書きますよね。こういう風な理由で、こういう風な展開になって、だからこうなるんですよ、と。ただ、『悪口論』はそういう感じじゃなくて、「バーと出てきました」という感じがある。それがすごく楽しくて。あのー、ほんとになんか、野坂昭如みたいな。ああいう感覚の。
〇小峰 野坂昭如に似てるんだ、これ。
〇かわすみ なんか、ああいう感じ。なんか野坂昭如って一文がすごく長くて、埴谷雄高とかも長くてけっこうバーっと長いですよね。
〇小峰 どんなん読んでるんですか、一体(笑)
〇 かわすみ いやいやいや。こうずっと続いていくような、文章にあまり切れ目がないような感じがすごく面白かったです。だから、私はわりと文学的な意味で捉えたという感じですね、どちらかと言うと。
〇小峰 僕の文章、短文ですけどね。
〇かわすみ 文章のつながりがわーっと続く感じで、はい。
〇小峰 確かに、僕は文章から声がするとよく言われるんですけど。
〇かわすみ そうそう、 ほんとにそういう感じがしました。生の、わーっと「しゃべりたーい」みたいな感じがすごく伝わってきました。
〇小峰 まあ、アジ文なんでね。アジテーションなんで。自己啓発本と言いましたけど、自己啓発本ってアジテーションじゃないですか。ちゃうんかな?
〇上原 そうですね。
〇小峰 だから、そういう気持ちで書いたというのがあったんです。
〇かわすみ だから表紙も、本当にそういう感じがするんです。読み終わってからもう1回表紙を見直したら、あ、この表紙は私は秀逸だなと思ったんですよね。
〇小峰 僕、この表紙、反対したんですよ。この表紙どうですか? 見て一番はじめに買おうと思いました? 思ったんですよね。(観客に)元々僕のこと知らなかったんですよね?
〇観客B いや、『平成転向論』を書かれたのは知っていました。それと『群像』(文芸誌)で新人賞を取ったやつは1回読んだことあるんですよ(小峰は第六十五回群像新人評論賞を受賞している)。で、『平成転向論』は積読しているんですけど、今回これが出て、次、このイベントがあるというのがあったから、読もうと思って買ったという感じでしたね。でも正直、「あ、この表紙か」と。
〇小峰 なりますよね。
〇観客B 正直ギャップがあった。出版社が違うということがわかった。僕は、百万年書房出版の外山恒一さんの本も持ってて、ちょっとギャップがあるなあと思いました。でもそういう路線でいっているんだなという感じです。
〇小峰 僕は最初これに反対していて。「これキモない?(笑)」みたいな。俺がメールで「売れへんやろ、これ。もっとクールなやつにしてや」みたいなやつ送ったら、すぐに編集の北尾さんから電話がかかってきて「いや、これが百万年書房史上一番いい表紙や。これでしか売れへんねん。これでいかせてくれ」と言われたんです。「これがいいんですよ。(本に)巻きましたか? 巻いたらめっちゃカッコいいですよ」と言うて。「ほんまかいな」と思ってました。今となっては、これでいいかなという感じなんですけどね。
〇観客B でも表紙見る限り、僕が見た本の中で一番赤裸々というか、バッと出てくるという。
〇小峰 すごくいい装丁の人(鈴木成一)に頼んでくれたらしくて、それを理由に押されました。「『同志少女よ敵を撃て』とかのデザインしている人だから」と説得されました。でも、この表紙じゃなかったら、もっとこじんまりした扱いになっていたと思うので、これでよかったとは思っています。
4.VOLとロスジェネの間で
〇観客C じゃあ、細かいとこですけど、その、赤木智弘とか杉田俊介には任せていられないというところ、もう少し聞きたいです。
〇小峰 雨宮処凛や生田武史や栗田隆子は別として、ロスジェネ世代の批評家とか論客の人は、お父さんとかが全共闘世代なので、負の遺産があって、左翼になりたいんだけど、運動に踏み込み切れないという雰囲気を、どうしても感じるんですよ。そんなことないですか?
ロスジェネの論客が20代や30代でデビューした時代は、今の70代の方が50代とかでバリバリでやってたときでしょ。だから、同じような感じでは、同じような文体で同じような左翼のノリでは、物書きとしてやっていけないということだと思います。もうちょっと内向的というか、活動にちょっと違和感を持っている人が論客としては多いイメージです。それを芸とかパフォーマンスだとかは思わないんですけど、そういう風な意識でやっている人が多いように思います。
でも、2015年に国会ではなく内閣が憲法九条の解釈改憲を行って、安保法制を通したという事態に象徴されるように、政府と立法府の関係性が勝手に入れ替わったちゃってるんですね。行政が立法府を従属化する。つまり、立法府があって、それが法を立てて、その法の主旨に則って行政が動く・執行するという形が基本なのですが、それが勝手に入れ替わって、行政府が立法府の上に立つという形に日本もなった。世界中どこもそうなんですけど、日本もそうなった。
で、そこで出てくる主体が、ネグリ=ハートのいう「マルチチュード」というやつです。有象無象とか群れとか群衆という意味ですね。マルチチュードは、人民(ピープル)と違って、代表を立てない。人民というのは自分たちで代表を立てて法律をつくって、行政府に法を執行してもらう存在です。自分たちでつくった法に自分たちで従う。だから、それは自分自身の統治でしょ、人民の共和国でしょという形で国家の主権者になるんですけど、いまや人民ではなく行政府が執行権だけではなく立法権も握っている。
このような司法府も立法府も弱いという状況では、人民としてふるまっても意味がない。立法府が役にたたないから。そこで、代表を立てずに直接的に行動するマルチチュード(有象無象とか群れとか群衆)や活動家主体が、行政府と直接的なぶつかり合いをするというのが、ネグリ=ハートの認識なんです。そして、2015年以降、日本も完全にそうなった。
そういう活動家の主体がやっぱり直接的な執行権力とぶつかり合いになっていく。そのときに、それを下支えするような言葉を、やっぱりロスジェネ世代の、雨宮処凛以外は持っていない。雨宮処凛もちょっと微妙なくらい、持ってないな。酒井隆史などの90年代にラディカリズムやっていた人は持っているけど、赤木さんとか杉田さんなどのロスジェネ論客は持ってないんですよ。
だから、そういう状況で動く「マルチチュード」を下支えする言葉がないといけない。逮捕者もいっぱい出るだろうし、深刻な状況になっていくのは目に見えているので、その状況を下支えする言葉がないといけない。が、それはロスジェネには任せられないので、じゃあ書くかということですよね。そういう認識が、2015年以降の認識としてあるということです。そういえば、山上徹也さんが安倍晋三を殺害したときに、編集から「これからますます小峰さんの言葉が必要になってくるから、頑張って書け!」と励まされました。
5.「バカでけっこう」(?)
〇観客B 帯は?「バカでけっこう」
〇小峰 もうこれは完全に編集が「これが好きなんです」という話ですね(笑)。(気になったのは)なんでですか?
〇観客B わりとこれを読む前に、自分の中でバカをどうするかという問題に興味があったんです。
〇小峰 あー。ネトウヨということですか?
〇観客B ネトウヨよりか、もっと政治に興味がない人たち。
〇小峰 無関心層?
〇観客B なんというか、たとえば、僕も、維新政治ということにちょっと反感はありつつも、でも維新から出ている金で、今はヘルパーとして働いているという。
〇小峰 維新からではないですよね。
〇観客B ではないですけど、維新が作ってる大阪府の行政のバリアフリーはかなり行き届いてる。先人の運動があったからこそなんですが、あるっちゃある。だから全てを否定できないなと思います。自分の葛藤としては、バカをどうするか。彼ら彼女らが今、政治的なものに意識を持っていないからこそ、今預かっている平和があると思う。全員目覚めてしまったら、フランス革命みたいに、トンデモないことになるということを目の当たりにしているという感じもしています。どうしようかなというのが、僕の中で葛藤としてあったときに、この一文を読んで、「もしかしたらそれって」と思ったんです。ちょっとこれは僕のゲスの勘ぐりだったかもしれませんが。
〇小峰 ゲスの勘ぐりとは違うと思います。ゲスの勘ぐりは、僕は他人の意図を勘ぐること(と定義している)ので。
〇観客B でもさっき言われた通り、『悪口論』は短いけど構築してて、隙がない文章だなと思います。特に飛躍がいい意味でないというところがあって、そこは読んでて面白かったです。
小峰 ありがとうございます。
観客B そうですね。そういう印象があったという話です。で、負け組になるということについて、橋本治という小説家が「革命とは、生活の質を全体に下げることである」と言っていました。全員が下げるということで成立するという話でした。それと似通った話なんだなという風に思いました。橋本治自身が、貧乏ということを肯定するという人でした。
〇小峰 あー、なるほど。ちょっと異論がありますね。まず、バカの話ですけど、僕は全員目覚めた方がいいと思っています。無知でいいことはない。しかし、目覚めるとか政治的になるというよりも、学びたいことを学ぶ。
〇観客B そうですね。賢く学ぶ的なことで、社会が賢くなるという話なんです。でも、単純にただ賢くなるのは難しいと思うし、普通にできるのかなという思いもある。僕も目覚めた方がいいと思う派でもありつつも、強制的に目覚めさせるのはさすがにちょっとどうかなと思います。なかなかそのへん自分の葛藤もあるという感じです。
〇小峰 お前、政治に関心持てよ!バシン!みたいな。
〇観客B それで、(政治に関心を)持ったところで、主体性が生まれるのかどうか。
〇小峰 絶対ないと思います。ただ、糾弾しないといけないことはあるとは思いますね。
あと、革命とは、全員の生活を下げることという話ですね。革命とは何かということをずっと考えてきたんですが、最近ようやくちょっと思い浮かびました。やはり法律なんですね。衆議院とか参議院とか憲法変えるとかじゃなくて、民法とか刑法とかも含めて法律の全体的な構造を変えるのが、革命と言われてるのかな、と。
〇観客C 先程の行政と立法の関係性は?
〇小峰 そうですね。先ほど述べたマルチチュードという主体はどういう主体かというと、僕の認識では、来たるべき法というか、未来の法を内包している主体なんですね。例えば、立法権力をどうするかとか、議会をどうするかということじゃなくて、オキュパイウォールストリートとか、BLMとかで生じる話し合いの仕方や指揮系統のあり方が、来たるべき法律の萌芽なんだと言います。そういう萌芽は法律に落とし込まないといけないなとは思います。だから、ちょっと法律勉強してるんですけど、法に落とし込むことが、いいか悪いかちょっとわかんないですけど、大事かなとは判断しました。
6.社会運動を継続する理由
〇かわすみ この本を書くきっかけについて質問があります。戦術の伝承ができにくくなったという話が出ていたと思うんですが、その原因がどこにあったのかという点についてはどう考えてますか?
〇小峰 それは中間団体みたいな労働組合とか部落解放同盟とか運動団体がなくなったことが大きいかなと思います。例えば、この間20代の人たちと一緒に行動したのですが、先輩といったら50歳とかですよ。やっぱりその間に大幅に抜けていると思う。まあそれは仕方がないとして、じゃあどうしていこうか、という問題ですね。
他ありますか? なければ最後に質問したいんですけど、さっきかわすみさんが「地道にやらないといかん」と言っていたじゃないですか。
〇かわすみ はい。
〇小峰 あんま報われないじゃないですか?
〇かわすみ そうですね。
〇小峰 それでも頑張ってやっていこうと思うのは、なんでなんでしょうね?
〇かわすみ なんでなんでしょうね。そこのところ、言葉にするのはやっぱ、難しいけど、いろんな理由があると思うんです。私の場合は、なんだろう、自分の意見を言うのがすごく苦手な人だったんですよ。すぐ「やっぱいいです、その通りで」と言ってしまう人間だったんですけど、運動をしていく中で自分が変わっていったんです。今もできるわけではないですけど、少しずつ言っていけるようになったりしました。
「今までこんなことやったことないな」ということを、運動に入った途端にやらされた。私もすごくびっくりしたのは、運動に入って間もない頃に、いきなり「集会の司会やって下さい」と言われて、全フリされたんですよ。それで、「えー?」となって、しどろもどろにやったら、なんとなくできたみたい、な。あと、それまでそんな大人数の前でしゃべったこともないのに、100人くらいの集会で「7分くらいしゃべって下さい」と言われて壇上に立たされるとか。いろんな経験したんですよ、街頭で歌えとか、ほんとにいっぱいあったんですよ。それで、もう必死でついていくうちに、自分の中で変わっていったことがいっぱいあった。で、そのことによって、自信がついて人前でしゃべるのが苦手じゃなくなった。いろんなことが自分の中で身についたんですね。
それと、意見を言ったら、なんとなくそれに受け答えしてくれる人もいた。怒る人もいたりするけど、でも、言えるということ、それがあったことがすごく大きかった。だから、自分が「ここに存在してもいいのかなみたいな」、そういう感覚は普通に仕事してたら起こらない。だから、そこに面白さがあるというのは感じています。例えば、前に重信房子さんのインタビューやったんですけど、そのときに重信さんも同じこと言ってましたね。自分は運動の中ですごく居心地が良かった、と。今までは普通の会社の中で上司と衝突したりしていた。でも、運動の中ではすごく居心地が良かったと言ってました。そのときに、「あー、一緒だな」と思ったんです。
だから、そういう理由もあるし、社会的に「やっぱりこれおかしいよね」と思うことに対して、アクションしていくとか、抗議していくとか、そういうことの中で、実際にちょっとでも仕組みが変わったときに、そういう経験が、「わ、変わるんだ!」と思うこともあった。もちろん、変わらないこともあります。変わらないことも多い。ただ、変わるんだと思ったこともあったし、そういうことだと思いますね、はい。
〇小峰 ひのさんどうですか?
〇上原 もう1回質問を。
〇小峰 社会運動って毎回、成果が報われるわけではない。しかも、コストもリスクもかかる。そういう中で、なんでやっていくのかな、と。なんでやろうと、それをやっていくというのは、合理的な発想ではないと思うんですよ、ある種。
〇上原 さっきその「バカ」の話とか出てたと思うんですけど、僕は社会運動こそバカだと思っています。僕も含めて。ほんとに生活の規律性がない人とか、ブルジョア社会で出世できなかったから、代わりに社会運動で出世してやろうという権力欲丸出しのやつとかもいて、
〇小峰 アハハハハハ。
〇上原 あと、単純に好きな人が運動現場にいるから、そこにいるやつとかいる訳です。で、それとの関係でいうと、社会運動ってバカばっかだし、あと『悪口論』とかでも扱われているように、社会運動の内紛もある。社会運動外よりも酷いところもあるわけですよ。政治力学がすごく働く。苦痛だなと思う場合がある。で、社会運動にコミットすることによって、解放感を味わう人もいれば、ひどく不信感が増すこともあったりすると思うんです。でも、やっぱり、社会自体は変えなきゃいけないというので、継続しなきゃならないというのはあるんですけれども。そういう中で、今後はその持続するというのが大事だと思っています。この本と同じ結論なんですけど、ハウツーとしての継続というのが大事だと思っていて、飯の食い方であったり、あるいは、ほどほどに性格破綻しない程度に生きていくやり方というのを集団で模索していくという必要があるのかな、と。答えになっているかわかんないですけど、そんなことを思います、はい。
〇小峰 社会活動のハウツーをある程度持っておく。例えば僕は、(ひのさんと)共通の知り合いの野宿者運動の人に、学生時代、「焼肉に行こう」と誘われたんです。「この人金あんのかな? 絶対ないやろ」と思ってたんですけど、「じゃあ、朝4時半に集合な」と言われたんです。4時半に(集合場所に)着いて、「どうするかな?」と思ったら、当然ですけど、肉屋のゴミかっさらって、公園でそのゴミの中のたばこの灰まみれの肉を洗って、みんなで食うという。めっちゃ美味かったけど、「焼肉食えるんや!」みたいな(笑)。
〇上原 天神橋筋商店街の。
〇小峰 そうです。
〇上原 僕は野菜をもらいました。
〇小峰 こうやって肉食うことできんねんな、一応。やろうとは思わないですけど。いざとなりゃあね、という。(肉は)超上物ですよね。
おわり