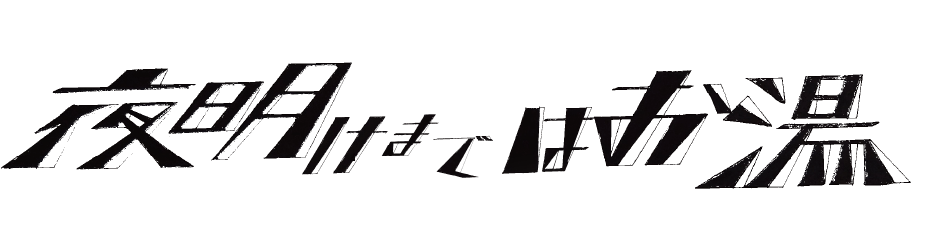2025.06.14 土
本とかのことです。メモの羅列です。
カラの箱にものをぎゅうぎゅうに詰めたくなるのと同じで、アイデアが出払って出がらしになった私はこの梅雨空で湿気を身体に纏うようにインプットに勤しんでいます。が、イベントをやるためにいろいろと忙しくしていないこのごろは、カイシャでの出来事とかに気を取られて、ちょっとした隙を狙ってくる軽いフラッシュバックに「あーーーーーー」と声を出していま・ここに意識を集中させ、脳の一部分を停止させながら本を読んだりするのが日常となってしまっています。なので、こうしてちょっと緊張して書いた人目につく文章でも表に出さないと、正気を保つのが難しそうに感じての更新です。
《ここ2ヶ月くらいの間に触れたもの》
●パウル・クレー展@兵庫県立美術館
あまりにも歴史的な知識がなさすぎて爆死しました。不勉強を恥じました。ナチスとバウハウスの関係なんて考えたことなかったです。クレーは詩が良いと聞いたのを今思い出してポチりました。読んだらまたなんか書きます。
●ノー・バウンダリーズ@国立国際美術館
越境をテーマとした現代美術作品の展覧会でした。沖縄に関する作品で、山城知佳子『オキナワ TOURIST』がとても好みでした。自他境界、国境、人種、について扱うものが多い中、米軍基地との境目に着目してるのが見ごたえあるなぁと思いました。境目のフェンスのど真ん前でアイスクリーム(たぶん沖縄のメーカーの)をべろべろ食べる姿に釘付けになりました。あとは、フェリックス・ゴンザレス=トレスの電球の作品が見れて嬉しかったです。
●太宰治『晩年』
とある読書会にて半年?くらいかけてひとつづつ読みました(参加できなかったやつは読めてない気がする)。わけわからなくて大変でしたが、「ロマネスク」がコントみたいでお気に入りです。「芸術家」という言葉の使い方が、適職診断で芸術家って出たら社会不適合者ってこと、と似たような意味を含んでいて、ほんとうにどうしようもないな〜と身につまされつつ滑稽に感じました。
●内堀弘『ボン書店の幻 モダニズム出版社の光と影』
これもとある研究会で課題本となっていました。実在した「ボン書店」の軌跡を追うノンフィクションのような感じなのですが、読んでいると完全なフィクションというか、もはやファンタジーみたいに思えてくるほど素敵な本です。巨木が生えている風景の写真が載っているのですが、なぜかそれに異様な魅力を感じました。そしてやはり印刷屋さんは偉大だと再認識しました。天使。
●エマヌエーレ・コッチャ『植物の生の哲学』
読書会で話に出てきて手に取りました。植物をもとに世界について書かれていて、「世界とは息吹である」なんて感覚的な言葉にハッとしました。ずっと、感覚的に読める言葉で書かれていてものすごく読みやすかったです。ちょっと字も大きいし。始終『風の谷のナウシカ』をイメージせざるを得なかったのがやっぱり自分の悪いクセだなと思ったり。エコロジー批判に行き着いていくからやっぱり通じるものはあるよなと思いながら、だけどエコロジー批判ってこういう風に言葉にできるんだ、と、とってもさわやかな気分になりました。
●三島由紀夫『豊饒の海 第一巻 春の雪』
これも読書会にて興味を持って。三島由紀夫ってなんか橋の話とものすごくエロい短編しか読んだことなかったんですけど、これも!まぁ!エロいというよりは「エロス!」って感じでもう、ずっと、ずーっと描写がエロス。快楽を読んでるのか、読んで快楽を感じてるのかわからない。こんな完璧な文章って存在するんだ・・・ってめっちゃびっくりしましたね。あと読めない漢字が多すぎて恥ずかしかった。けどめちゃくちゃ面白くてあっと言う間に読めました。
●まるよのかもめ『ドカ食いダイスキ!もちづきさん』
とにかく食べるもちづきさん。たまにドカ食いするとかじゃなくて毎食なんだな・・・。グルメ漫画としての一面も絶対にあるけど、美味しそうには見えないというか・・・。この種の強迫行動には身に覚えが無いでもない。わかる〜、と、ちょっとそれは無理かな、が交互にやってきて、もちづきさんが代わりに食べてくれるから私は沢山食べなくても大丈夫かも!みたいな感覚になったから結果的に読んで良かったです。
●レオス・カラックス監督作品『IT'S NOT ME』
42分とかしかない短い映画なんですが、体感は5分。あっと言う間に終わりました。リズム感が刺激的で飽きるひまが無かった。「汚れた血」「ポン・ヌフの恋人」のシーンが挟まれてて、あー私はなんでアレックス青春三部作のDVDセットを売ってしまったんだ・・・もう自分には必要ないと思ってたけど、やっぱりたまには観ないと心が枯れてしまうこれは・・・!ってなって再購入しました。あと最後に人形劇があって、人形好きの私、泣きました。
今触れてるもの
●吉村明美『薔薇のために』
ネット広告から気になって、途中まで無料読みして、めちゃくちゃ面白くて文庫本購入して読んでるところです。絵が綺麗。好き。セリフが美しい。好き。北海道が舞台なのもなんか好き。時代はもちろん感じる。でも、少女漫画をあまり読んで来なかったから、なんかとても嬉しい。
●三島由紀夫『豊穣の海 第二巻 奔馬』
続きですね。面白い!
よく触れてるもの
●お文具のアニメ
2020年からYouTubeで活動してるお文具のアニメさん。まさに私が無職引きこもりをやっていたときに救ってくれた存在です。ちいかわも良いけど、お文具さんも良い。一番好きなのは登場するキャラクターみんなのモーニングルーティーンとナイトルーティーンのアニメです。
●ショート動画
死ぬほど見てます。カイシャのこと考えたくないって思うとめちゃくちゃ見ちゃいます。ツイッター止めたときみたいに、止められたらいいのになぁ。
●刺身タンポポさん
関西マニアック散歩のユーチューバーさん。Wikipediaの知識もあるんだと思うけど、実際に歩き回って撮影されてるのが驚愕。海水プール、行ってみたい。
●安住紳一郎の日曜天国
ただただ好き。
●音楽
スティーブ・ライヒ、宇多田ヒカル、テニスコーツ、FKJ、fka twigs、ツジコノリコ
気になってるもの
『おそいひと』と『どうすればよかったか?』。どっちも映画で、前者はDVDを購入してて後者は上映中です。障害や差別についてはずっと関心を持ってるのですが、いかんせん重いのでサッと観れないのです。『おそいひと』はサントラをworld's end girlfriendがやってるってことでそちらもとても楽しみなんですけど・・・。考えるために観るというよりは、知るために観るんですが、学習という感覚でもなく、探してるな、と思います。何を探してるのかはっきりとは分からないんですけど。『どうすればよかったか?』はポルノになり得ない映画なのだろうなぁ、と予想したりしていて、それはやっぱり精神障害が目に見えない障害だからなんだろうと考えたりしています。観ても、たぶん、他の障害を扱った映画のように「快楽」を与えたりはしないだろうな、なんて。なんてったって「映えない」んだから。こんな風に構えずに観に行ったほうが絶対良いんだろうな・・・。
富岡多恵子の古本いっぱい買ったのに全く読んでないなそういえば!
読んでくださってありがとうございます。
おわり
2025.03.11 火
5回目のオープンアトリエを終えて
展覧会をやるっていうのじゃないとよくわからないようなアイデアが溜まっていて、それを形にするために2023年10月からイベントを行ってきました。修士課程を出たのが2017年で、初めての個展はレンタルギャラリーで2018年5月に開きました。そこから5年間、私の人生の98%がそうであったように、アイデアはあっても制作も発表もできず、毎日ずっと焦ったりイライラしたり世界を呪ったりして過ごしていました。
ギャラリーを借りるのはとてもお金がかかります。私が借りたギャラリーは2週間で13万円くらいかかったと思います。2週間で13万円で、制作費や運搬費やらを考えるとだいたい20万円くらい吹っ飛びました。当時の私の手取りは月17万円、日本学生支援機構に毎月2万4千円くらい持っていかれ、かつ、10年目のひとり暮らしをしていました。お金をうむ作家になるのは身体の内側からしてとうてい無理あるし、自分で自分のパトロンをやって好き勝手に制作と発表を続けるにはどうしたらいいのだろうといつも通り世界を呪っていたところ、出逢ったのがタツタビル401号室でした。自宅以外に部屋を借りるなんて贅沢なことを自分ができるとは思ってもみませんでしたが、2023年3月はなんとかそれが可能な状況でしたし、その状況を何が何でも維持しよう、むしろ向上させようと思いました。
夜明けまではお湯では自分の作品の発表だけでなく作家を招いてのイベントも行ってきました。その理由には「博士課程に進むよりもよりよく研究し、学ぶにはどうしたらいいか」というちょっとした抵抗が挙げられます。というのも私は順当に芸術学修士号を取得したのではなく、実家の教育方針によって普通科の高校から経営学部に進んだあと当然のように留年し、奮起して学部5回生から2年ほど科目等履修生としてある大学の彫塑研究室に通って具象彫刻を学び、場所を変えて研究生を1年やって石を彫り、それから修士課程に入ってコピー用紙で人形を作って脱出した、という経歴です。博士課程に進むかどうかそうとう悩みましたが、結局、治療用装具の製造職に就きました。大学を自分の場所だと感じられたら違ったのかもしれませんが、自分が自分の場所だと感じられた場所ってこれまであったのかというと、そんなの無かったし、今回も違ったな、という感覚がすごくあった気がします。でも研究したいこと、学びたいことがありました。それが、「場所を作ること」でした。プランをきっちり考えていたわけではありませんが、おかげさまでリズム感のあるストーリーを編んでこられたように思います。
私は夜明けまではお湯を作ってよかったと思っています。2025年5月からしばらくは、軽くリフォームしたりして、雰囲気を変えて制作中心の場所にしていきたいと思っています。今度からの「オープンアトリエ」はたぶん本当に「オープンアトリエ」らしいそれになりそうです。